学生時代、古文の勉強に時間を割く価値は感じられないかもしれません。
しかし、古文の学習を通して、昔の日本の文化や生活習慣を感じ取るのは、とても趣深いことです。
今回の記事では、僕の受験生時代を振り返って、どう古文と向き合っていけば良いのか解説していきます。
古文を学習するメリット
まずは結論。
古文は社会に出てから、実用的に役立つ人は学者か予備校講師くらいです。
しかし、これでは答えになっていませんね。
なぜ、貴重な若い時間をさいて古文を勉強するのか?
僕は二つの理由があると思っています。
- 自国文化のルーツを知る
- 外国語学習の練習
自国文化のルーツを知る
海外の人は学校教育で自国の歴史をきちんと学んでいます。
それに対して、日本人は高等学校において日本史が必修科目ではなく、自国の文化歴史をあまりよく知らない大人で溢れているのが現状です。
自国のルーツを深く知ることは、異文化の理解の基盤になります。
そういう意味でも、古文を学ぶことには一定の価値があるのではないかと思います。
外国語学習の練習になる
古文の文体は現代の日本語には一部を除いてほとんど残っていません。
しかし、英語と違って何となくの意味は読み取れるはずです。
古文で単語学習や訳出の練習をすることを通して、英語学習の仕方のヒントを探るのも古文との一つの付き合い方なのではないでしょうか?
古文を勉強するポイント
- 文法
- 古典常識
- 語彙
①文法
昔の日本語は現代の日本語よりもシステマチックな文法体系を持っていました。
そのため、一度しっかり文法を押さえてしまえば、文章をきっちり理詰めで分析することができるようになります。
日本語の文法って意外と良い加減ですw
 アオミネ
アオミネ助動詞の活用はもしもし亀よ〜♪のリズムで覚えました
②古典常識
古文を読む上でもう一つ大切なのが、文からその情景を想起することです。
家の間取りや調度品から当時の風習にいたるまで、古文常識をベースにイメージすることが、場面の正確な理解につながります



マンガ日本の古典を読んで、有名作品のストーリーを押さえておくのもアリ
③語彙
最後は結局これです。
現代語と語感が似ている語もありますが、同型で意味の異なる単語もあるので注意です。



いとおかし
古文のオススメ参考書
読み解き古文単語
少し古い本ですが、今で言うところの速読英単語と同じコンセプトで、本文のなかに使われている単語を生きた形で覚えられる参考書



新しい参考書で同じコンセプトのものを知ってる方はお問合せの方からぜひお知らせください
栗原の古文単語教室
文献学の視点から見た古文単語の成り立ち、意味の派生を系統的に理解できる参考書



コンセプトがとても好きです
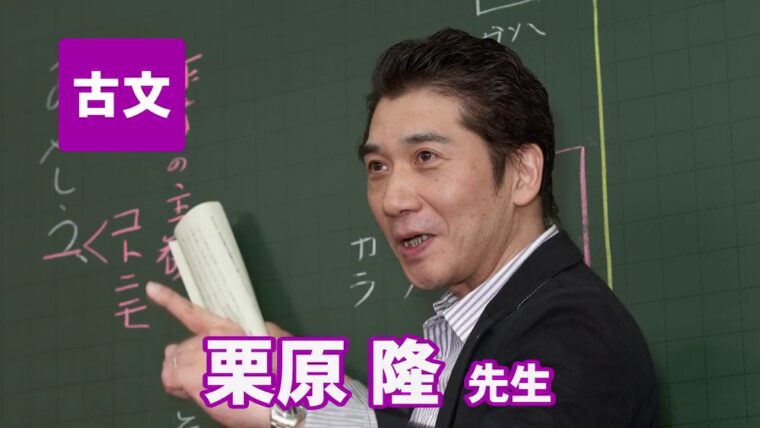
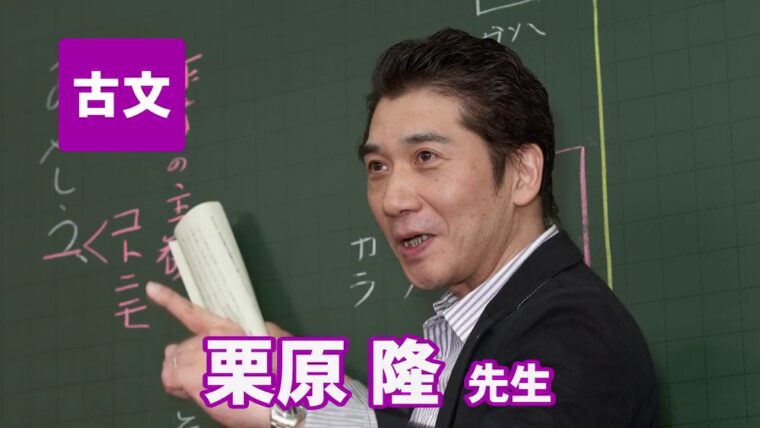
マドンナ古文常識



読みやすいです
鉄緑会 東大古典問題集
問題集として使っていました。
本文の一行に対して、品詞分解や背景知識について数ページに渡る解説が展開され、とてもためになります。
1〜2年のうちに10年分やっておくと今後、古典にかけなければいけない学習時間の目安がつくと思います。



解説の語り口調に中毒性があります
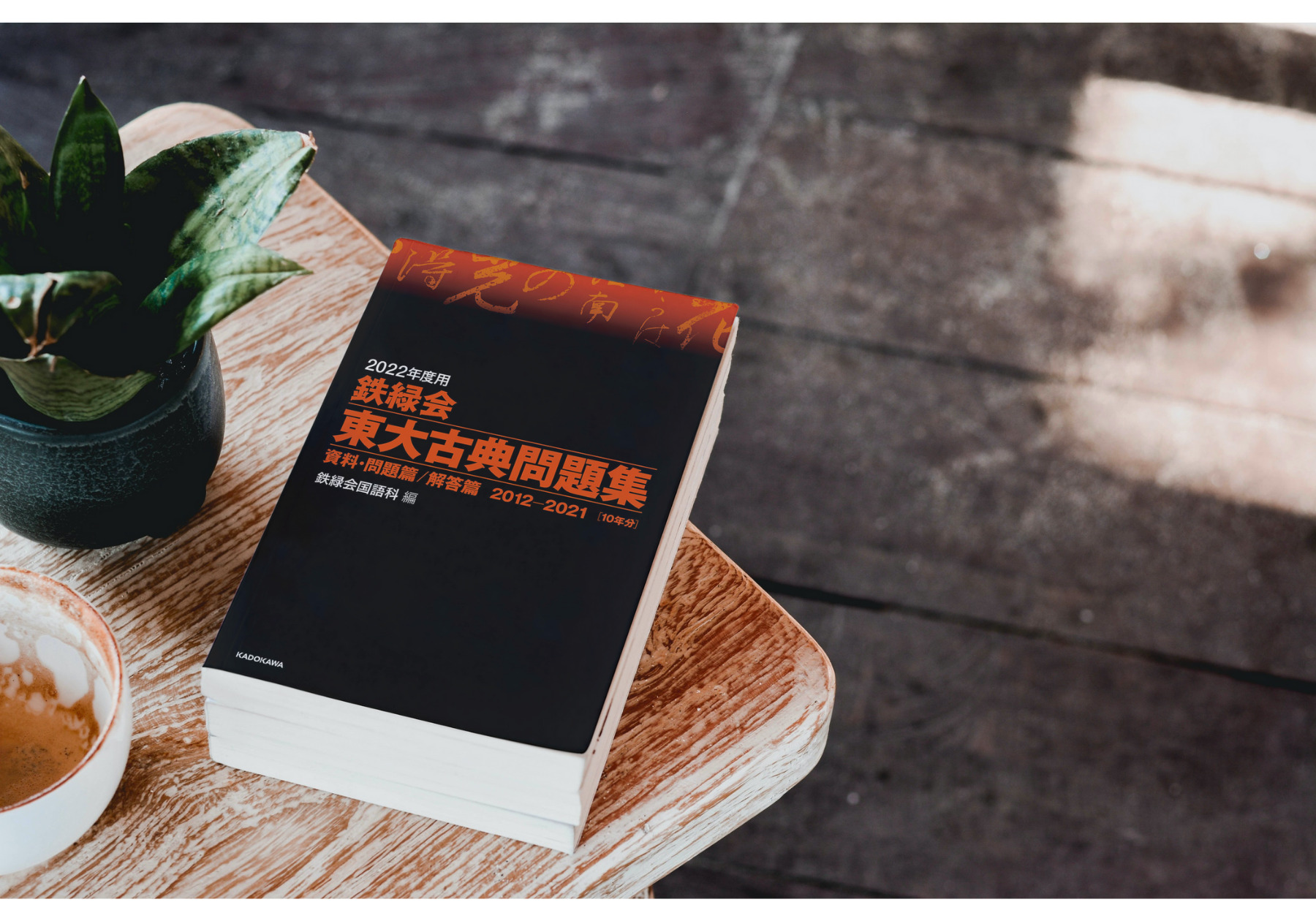
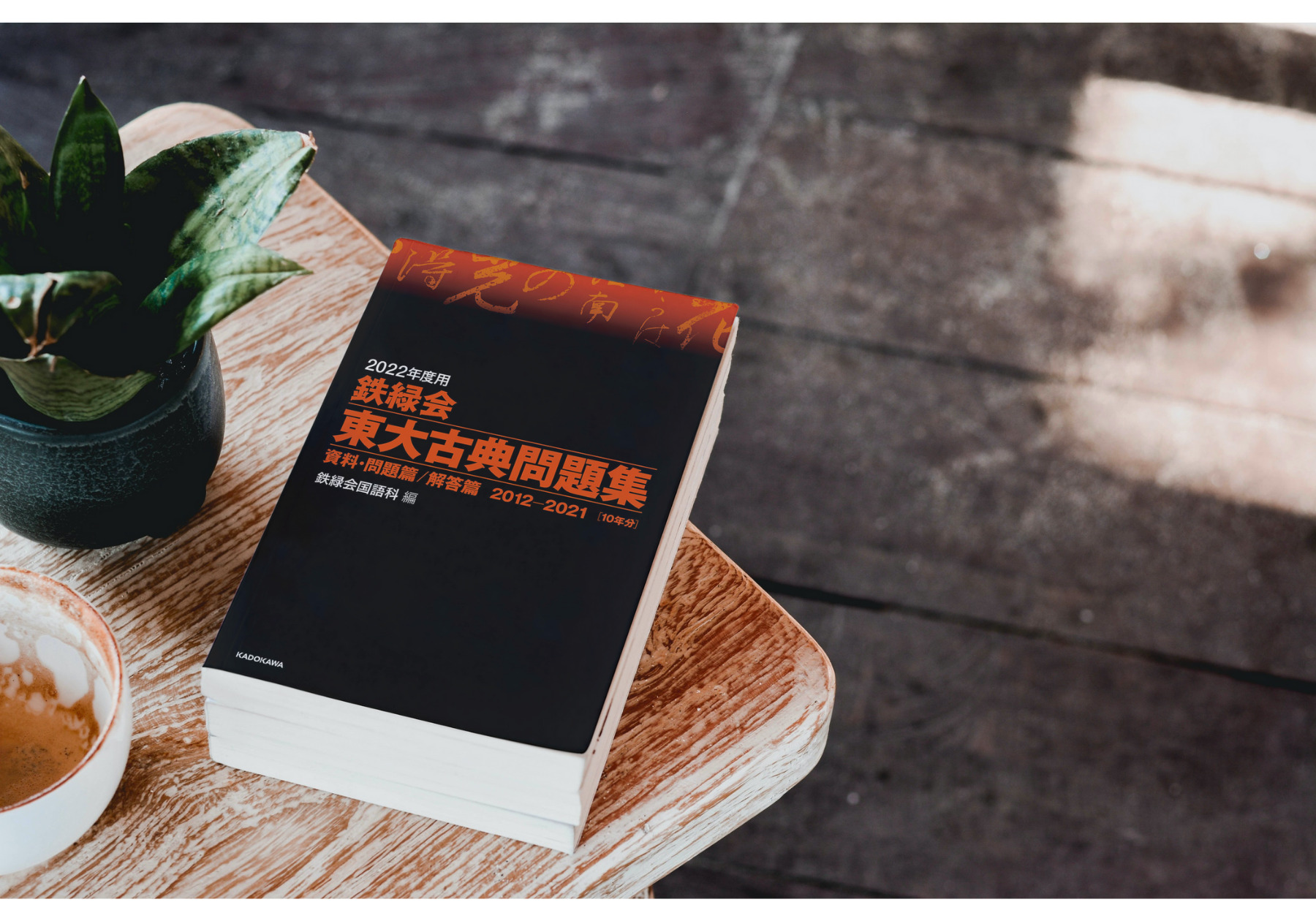
あさきゆめみし
源氏物語には古文を学ぶ上で必要なエッセンスが詰まっています。
後の時代の古文も話の展開を踏襲している例が多々見られので一読しておくことをオススメします。



漫画なので、楽しく読めます
講談社学術文庫
読んだのは「竹取物語」「伊勢物語」「土佐日記」「蜻蛉日記」「平家物語(長すぎて途中で挫折)」です。
詳しい注釈付きで古典に親しむことができます。サイドリーダー感覚で読んでました。



余裕がある人も特にやる必要はありません。
古文の勉強法に関するよくある質問
- 古文の勉強は将来、役に立つ?
-
学者か予備校講師になれば、実務的に役立ちます。
- 古文の学習で意識すべきことは?
-
文法の正確な理解、豊富な語彙、情景を豊かにイメージできる古典常識
- 古文を勉強するメリットは?
-
自国文化のルーツを知ることができます。また、外国語を学ぶ良い練習にもなります。





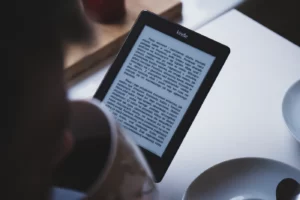



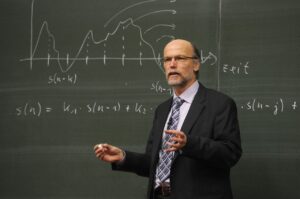


アオミネ