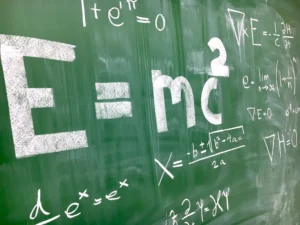物理のためのベクトルとテンソルを読むべし
簡単解説:テンソルとは
2冊目に紹介する本の冒頭では、以下のように説明されています。
テンソルとは, 大きさと複数の向きによって特徴づけられる物理量の, 数学的な表現である.
物理のためのベクトルとテンソル(ダニエル・フライシュ, 岩波書店, 2013)1.1節
しかし、この文章だけでは、ベクトルのような大きさと単一の向きによって特徴づけられる物理量の定性的のイメージは浮かぶかもしれませんが、複数の向きとなると話は変わってきます。
同書の後半では、以下のようにテンソルは定義されます。
ランク n のテンソルとは, 座標変換に対して普遍な量になるように複数の方向の標識(基底ベクトル)と組み合わされた, テンソル成分と呼ばれる(3次元空間では)3n個の値の配列で表される量である.
物理のためのベクトルとテンソル(ダニエル・フライシュ, 岩波書店, 2013)5.1節
テンソルについての理解度の評価基準として、この説明が理解できることが第一目標になります。
続いて、テンソル計算ができるようになれば、手を動かしながら読むことで専門書も読み進めることができるはずです。
(テンソル計算は煩雑なので、時間はかかると思います。)
テンソル解析のおすすめ教科書
この記事では, 大学物理の中でも流体力学や一般相対論を独学する上で避けては通れない1テンソル(tensor)について、数学的に厳密なものではなく直感的に分かりやすい教科書を難易度別に3冊紹介します。
初級者向け:
オススメの教科書:
物理とテンソル(中村純, 共立出版, 1993)

極めて平易な言葉で書かれているので、サクッと読める1冊。
しかし、言葉を尽くすあまり、少し冗長に感じる人もいるかもしれません。
これまでテンソルを理解しようとして挫折した経験がある人は、初心に帰ってこの本から学習を進めてみてください。学生で初めてテンソルに挑戦する方であれば、次に紹介する本から読む方がスムーズに学習が進められると思います。
中級者向け:
オススメの教科書:物理のためのベクトルとテンソル(ダニエル・フライシュ, 岩波書店, 2013)

物理学習者向けのテンソル解析の入門書として、今後スタンダードになるであろう一冊。
出版年も比較的新しく、全6章で前半はベクトル、後半はテンソルについて解説しています。
必要最低限だけ学習して、物理的内容に早く踏み込みたい方は1.1節, 4節, 5節だけ読めば、専門書の記述にも対応できると思います。
上級者向け:
オススメの教科書:
テンソル解析(田代嘉宏, 裳華房, 2006)

紹介した3冊の中では一番数学書に近い書き方をされた一冊。
しかし、一般化せず、3次元ユークリッド空間に内容を制限していることで、物理学習者にとっては非常に学びやすい一冊になっていると感じました。
補足・注釈
補足
物理の各分野におけるテンソルの使用例を紹介します(加筆予定)
- 力学…慣性テンソル
- 流体力学…応力テンソル
- 一般相対論…リッチテンソル
まだ中身を確認できていない本も下記にまとめておくので、各自参考にしてみてください。
注釈
- 他には、機械学習などのプログラミングでもテンソルの理解が必要です。Pythonで機械学習を行うのであれば、Google社が開発したTensorFlowというライブラリのお世話になると思います。 ↩︎